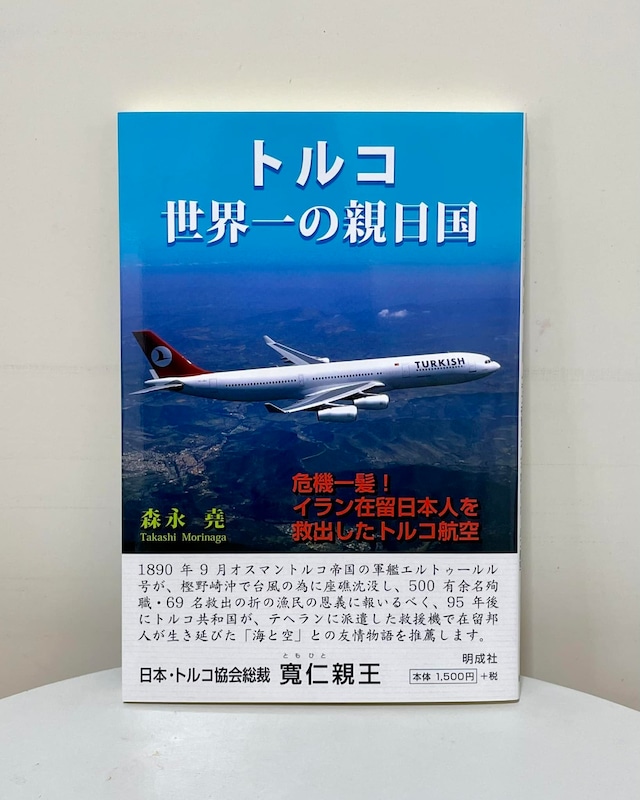Item
戦後教育改革半世紀 ―世界をリードする日本へ
髙橋史朗/著
四六判288頁
「戦後とは何か」という疑問を解き明かすため、いざ米国へ。占領文書研究に臨み、教育改革の一歩を踏み出す。
戦後教育、臨教審、歴史教科書問題、いじめ、学級崩壊、感性教育、教育基本法改正、児童虐待、親学……。
七十余年の人生を振り返り、日本教育の新たな展望を明らかにする。
【内容】
一 戦後史の検証を決意した理由
学園紛争最盛期、左翼学生との激しい対決の中で渇望した、時代を領導する感化力。大学キャンパスで抱いた「戦後とは何か」という問いが、その後の人生を決定づけることとなった。
二 占領文書二四〇万ページ研究に臨んだ米国留学
戦後教育学の定説=「教育基本法は戦前の教育勅語を否定して成立した」の誤謬を自身の研究によって見事証明。決意の渡米による占領文書研究が、戦後教育学の新たな地平を切り拓いた。
三 臨教審・民間教育臨調が目指した教育基本法改正
平成十八年十二月に実現した教育基本法改正。戦後教育改革史に輝く金字塔は如何にして打ち立てられたのか。議論の渦中に身を置いた著者だからこそ語れる舞台裏とは。
四 教科書誤報事件と歴史認識問題
今日まで続く〈歴史戦〉の最前線で戦い続けてきた著者。全ての問題に通底する「日本という国家に対する悪意や不当な構図」を払拭するための戦いの軌跡を描く。
五 いじめ・不登校を克服する感性教育
一九八〇年代以降、社会問題化した子供たちの心の病。祖先からいただき、子孫へ受け渡してゆく命の連続性を如何に育むべきか。保守・革新を越えた新たな取り組みが始まった。
六 師範塾と親学の提唱―主体変容の教育改革
〈「研究」はあるが「修養」がない教員研修〉〈親が親としての学びを得ることのできない今日の教育・社会の欠陥〉の二つに着目。子供を育てる基盤となる親、教員の力を養うための実践の記録。
七 世界をリードする日本へ
「日本と世界をリードする新たな教育モデルを創造する」をスローガンに立ち上げた髙橋塾。不易と流行の調和を図り、時代の最前線に打って出る意欲は、いまだ衰えるところを知らない。
四六判288頁
「戦後とは何か」という疑問を解き明かすため、いざ米国へ。占領文書研究に臨み、教育改革の一歩を踏み出す。
戦後教育、臨教審、歴史教科書問題、いじめ、学級崩壊、感性教育、教育基本法改正、児童虐待、親学……。
七十余年の人生を振り返り、日本教育の新たな展望を明らかにする。
【内容】
一 戦後史の検証を決意した理由
学園紛争最盛期、左翼学生との激しい対決の中で渇望した、時代を領導する感化力。大学キャンパスで抱いた「戦後とは何か」という問いが、その後の人生を決定づけることとなった。
二 占領文書二四〇万ページ研究に臨んだ米国留学
戦後教育学の定説=「教育基本法は戦前の教育勅語を否定して成立した」の誤謬を自身の研究によって見事証明。決意の渡米による占領文書研究が、戦後教育学の新たな地平を切り拓いた。
三 臨教審・民間教育臨調が目指した教育基本法改正
平成十八年十二月に実現した教育基本法改正。戦後教育改革史に輝く金字塔は如何にして打ち立てられたのか。議論の渦中に身を置いた著者だからこそ語れる舞台裏とは。
四 教科書誤報事件と歴史認識問題
今日まで続く〈歴史戦〉の最前線で戦い続けてきた著者。全ての問題に通底する「日本という国家に対する悪意や不当な構図」を払拭するための戦いの軌跡を描く。
五 いじめ・不登校を克服する感性教育
一九八〇年代以降、社会問題化した子供たちの心の病。祖先からいただき、子孫へ受け渡してゆく命の連続性を如何に育むべきか。保守・革新を越えた新たな取り組みが始まった。
六 師範塾と親学の提唱―主体変容の教育改革
〈「研究」はあるが「修養」がない教員研修〉〈親が親としての学びを得ることのできない今日の教育・社会の欠陥〉の二つに着目。子供を育てる基盤となる親、教員の力を養うための実践の記録。
七 世界をリードする日本へ
「日本と世界をリードする新たな教育モデルを創造する」をスローガンに立ち上げた髙橋塾。不易と流行の調和を図り、時代の最前線に打って出る意欲は、いまだ衰えるところを知らない。